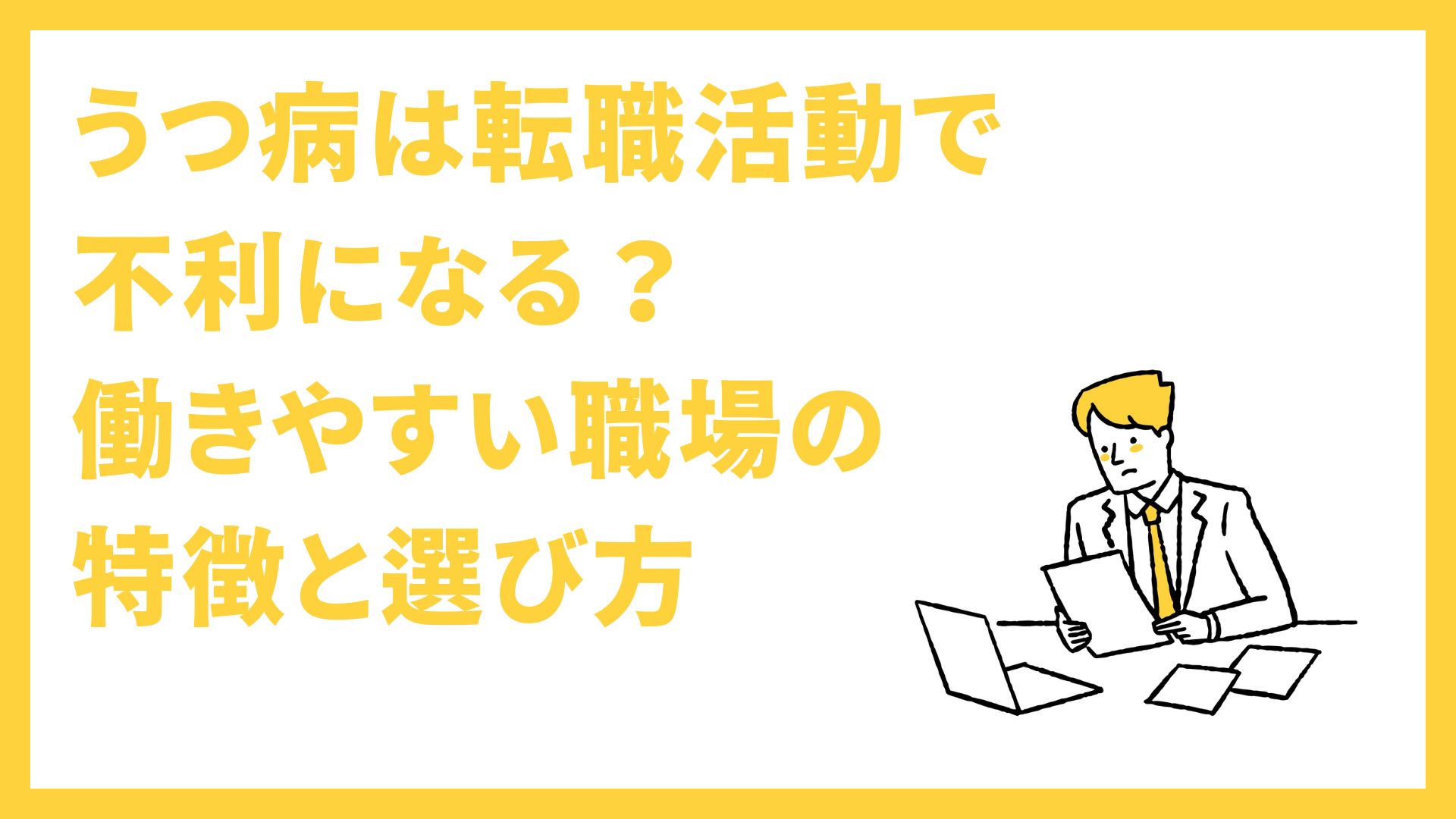うつ病は、気分が落ち込み、さまざまな意欲が低下する気分障害の一つです。働く意欲の低下や、疲れやすい・眠れないといった身体的な不調が生じることもあります。
転職を希望する方のなかには「うつ病が転職に不利になるのでは」と心配する方もいるでしょう。しかし、適切な準備と情報があれば、うつ病と向き合いながら自分らしい働き方を見つけることは可能です。
本記事では、うつ病のある方が転職活動を進めるうえでのポイントや注意点、成功のためのヒントを解説します。
うつ病でも転職は可能?現状とデータをもとに解説

令和5年におけるうつ病を含む精神障害者の新規求職申込に対する就職率は、43.9%でした。就職活動をしている方の半数以上が就職できていない現状から、うつ病の方の就職の難しさがうかがえます。
一方で、2018年の障害者雇用促進法改正により、精神障害者が雇用義務の対象となったことで、民間企業における実雇用率は増加傾向にあります。障害者雇用促進法は、一定規模以上の事業主に、常時雇用労働者の一定割合以上の障害者雇用を義務付ける日本の法律です。この法改正が、精神障害者の雇用促進に一定の効果をもたらしていると考えられます。
転職活動の前にうつ病経験者が行うべき3つのこと

ここからは、うつ病経験者が転職活動前に確認しておくべき3つのポイントを解説します。
うつ病の治療を進めるなかで、症状が一時的に改善すると「早く社会復帰しなければ」「この状況を変えたい」といった焦りや不安から、衝動的に決断してしまうケースが見受けられます。
しかし、無理な判断をしてしまうと、かえって症状が悪化する場合もあるためじっくり検討しましょう。
主治医への相談
うつ病で転職を考える際は、まず主治医に相談しましょう。ご自身が転職に意欲的であっても、症状により休養が必要な場合もあります。
主治医の許可を得てから無理のない範囲で活動を始め、現職での復帰も視野に入れることが大切です。自己判断せず、必ず主治医と相談しながら進めましょう。
現在の体調と転職のタイミングの確認
転職を考える際、最も重要なのは体調です。まずは主治医に相談し、就職活動に取り組めるか、適切なタイミングを見極めましょう。
体調が不安定なまま転職活動を進めると、症状悪化や早期離職につながる恐れがあります。焦らず、専門家の意見を聞きながら、心身ともに無理のない範囲で始めることが大切です。
休職期間と現在の経済状況
会社の休職制度により定められた休職可能な期間と、ご自身の経済状況について把握しておきましょう。
うつ病を含むメンタルヘルス不調での休職期間は平均3か月半と言われています。勤務継続が難しい場合は、無理せず休職制度の活用を検討しましょう。
休職中は、傷病手当金や自立支援医療制度などの支援を受けられる可能性があります。該当する制度や支援内容については、会社の人事担当者や主治医に相談してください。
うつ病の方の就職・転職相談受付中!障害者雇用でテレワークができる案件が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
うつ病でも働きやすい職場・企業の選び方

うつ病を抱えながら働くには、職場選びが極めて重要です。再発を防ぎ、安定して就労を続けるためには、企業文化、業務内容、サポート体制など複数の要素を考慮する必要があります。
ここでは、うつ病の方にとって働きやすい企業を選ぶポイントを解説します。
メンタルヘルス対策の充実度
うつ病への理解がない会社へ転職すると、再発時に退職を迫られるリスクがあります。再度の立て直しは精神的負担が大きいため、病気や障害への理解と配慮がある職場を選びましょう。
その見極めには、ストレスチェックの義務化をはじめとする企業の健康経営への取り組みやメンタルヘルス対策の充実度、メンタルヘルス研修や産業医面談の実施状況、そして経営陣の理解度も重要な要素です。
残業時間の実態と有給休暇の取得しやすさ
うつ病の方の転職では、残業時間の実態と有給休暇の取得しやすさが極めて重要です。残業が少ないことは心身の負担を軽減し、安定した就労を促します。
また、有給休暇を取得しやすい環境は、体調不良時や必要な休息を無理なく取れるため、再発リスクの低減につながります。企業のワークライフバランスへの意識をしっかり確認しましょう。
過度なプレッシャーやノルマの有無
過度なプレッシャーやノルマがないか確認しましょう。高すぎる目標設定や成果主義は精神的負担を増大させ、症状の悪化や再発につながりかねません。
求人情報だけでなく、面接時に業務内容や評価制度を具体的に質問し、自身のペースで働ける環境か見極めることが重要です。
職場の雰囲気やコミュニケーションの取りやすさ
うつ病の方にとって、転職先が風通しの良い環境であることは非常に大切です。上司や同僚と円滑にコミュニケーションが取れ、気軽に意見や相談ができる職場は、心理的な負担を大きく軽減でき、安心して働けます。
面接では職場の雰囲気やコミュニケーションの取り方について質問し、協力的な社風であるか見極めましょう。
福利厚生とサポート体制
安定して働くには、充実した福利厚生と手厚いサポート体制が重要です。具体的な福利厚生やサポート体制としては、次のようなものが例として挙げられます。
・病気休暇・休職制度
・医療費補助制度
・傷病手当金
・カウンセリングサービス
・専門家への相談窓口
・復職支援プログラム
これらの福利厚生やサポート体制の詳細は、企業の採用ホームページや面接で確認しましょう。企業内の産業医や産業保健スタッフが対応するか、外部機関の専門家が対応するかについても企業により異なります。
通勤時間と勤務形態
通勤時間と勤務形態は心身の負担に大きく影響します。通勤時間が短いほど疲労を軽減でき、体調管理もしやすくなります。
また、フレックスタイム制や在宅勤務といった柔軟な働き方を選べる職場であれば、体調に合わせて働くことも可能です。ご自身の症状に適した働き方を見つけましょう。
「障害者雇用枠」の有無
うつ病の方の転職では、障害者雇用枠も選択肢の一つです。この枠では、企業が障害のある方の特性や配慮すべき点を理解しているため、働きやすい環境が整備されており、合理的配慮を受けながら就労できる可能性があります。
ハローワークや障害者専門の転職エージェントなどを活用し、ご自身の状況に合った求人を探してみましょう。
うつ病の方が転職で利用できる支援サービス・制度

うつ病を抱えながらの就職活動は、一人で悩まずに専門機関のサポートを活用することが大切です。ここでは、就職に関する相談から求人紹介、職場定着支援まで、うつ病のある方が安心して転職活動を進められる就職支援機関を紹介します。
ハローワーク
ハローワークには障害者雇用専門の職員や相談員がおり、専門知識に基づいた求人紹介や訓練など、幅広い支援を提供しています。
一般雇用にするか、障害者雇用にするか迷う際も、まずはハローワークの窓口へ相談してみましょう。状況に合わせた求人紹介や面接への同行などきめ細やかなサポートを受けられます。
転職エージェント
転職エージェントは、求職者と企業をつなぐプロです。非公開求人の紹介や条件に合った企業の選定、履歴書添削、面接対策といった手厚い選考サポートが受けられます。
さらに、体調や希望に配慮した企業とのマッチングを支援し、直接伝えにくい配慮事項もエージェントを通して交渉してもらえるため、安心して転職活動を進められるでしょう。
うつ病の方が応募できる障害者雇用の案件が豊富!転職エージェント「FLEMEE」に相談したい方はこちら
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害のある方の就職と職場定着を支援する公的機関です。うつ病の方には、専門の職業相談や職業評価、職場適応訓練などを無料で提供します。
個々の状況に応じた支援計画を作成し、ハローワークや医療機関と連携しながら、就職活動から入社後のサポートまで包括的に支援してくれます。
就労移行支援事業所
就労移行支援は、障害のある方の一般企業への就労を支える通所型福祉サービスです。全国に約3,300ヶ所の事業所があり、就職準備から職場定着まで幅広くサポートしています。
具体的には、ビジネスマナーやスキル習得、自己管理やセルフコントロールの訓練といった転職活動に役立つカリキュラムを受けられます。
まとめ

この記事では、うつ病と向き合いながら転職活動を進める方法や、安心して働ける職場探しのポイントについて紹介しました。転職活動を成功させるには、主治医と相談しながらじっくり検討することが重要です。
障害者雇用でテレワーク可能な求人に特化した転職エージェント「FLEMEE」では、求人紹介だけでなく、障害者雇用の転職活動に関するサポートも行います。
うつ病を抱えながらの転職に不安を感じる方は、ぜひFLEMEEにご相談ください。