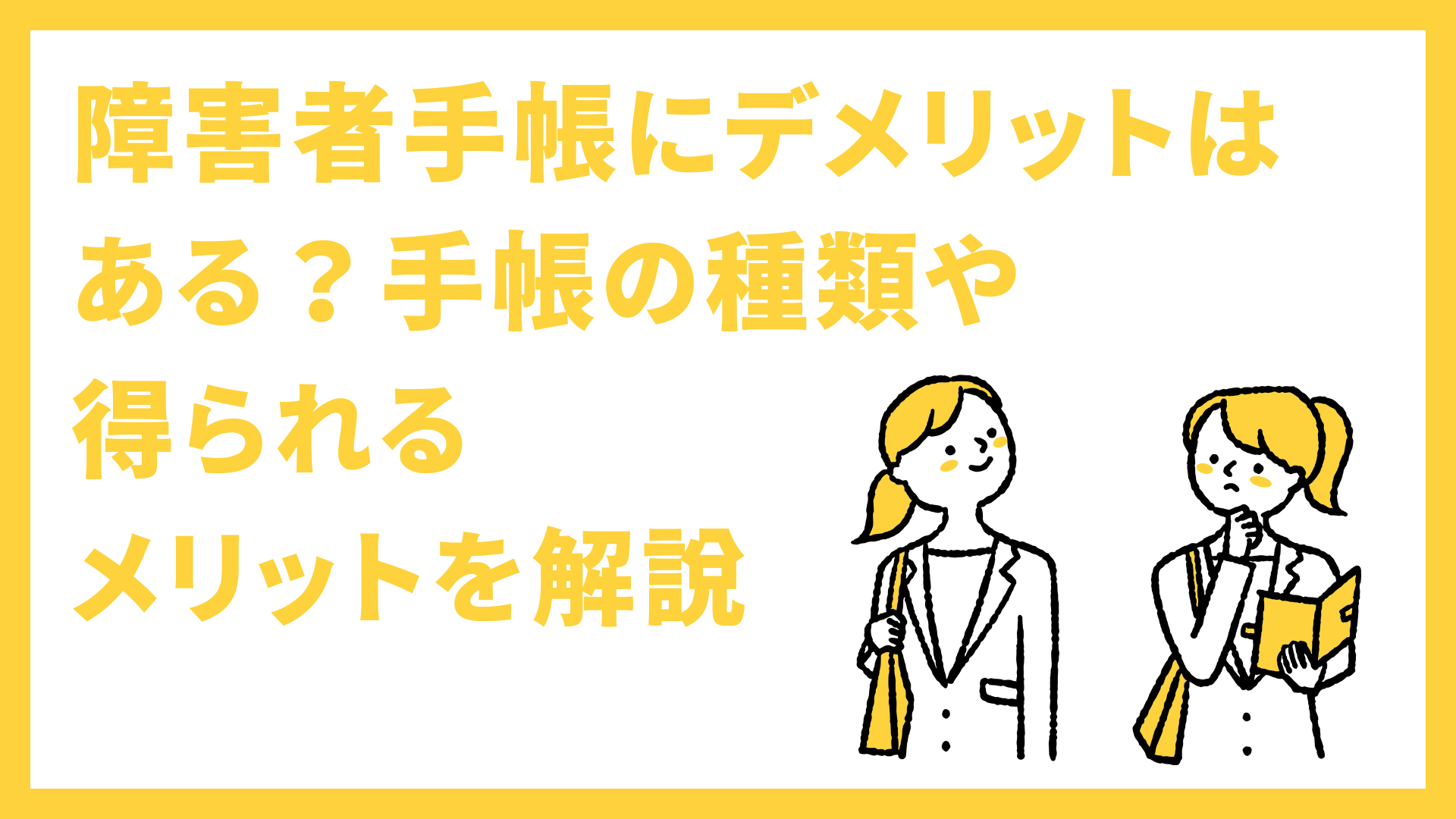障害者手帳は、障害を持つ方が必要な支援を受けるための公的な証明書です。多少のデメリットはありますが、それ以上のメリットを享受できるので、積極的に取得したほうがよいでしょう。
この記事では、障害者手帳の基礎知識や障害に応じた3つの種類、取得することで得られるメリットやデメリットについて解説していきます。障害者手帳を取得するか迷っている方や、障害者雇用枠での就職を考えている方にとってのヒントになれば幸いです。
障害者手帳を取得して働きたい方の相談を受付中!テレワーク特化型転職エージェント「FLEMEE」はこちら
障害者手帳の基本を知ろう
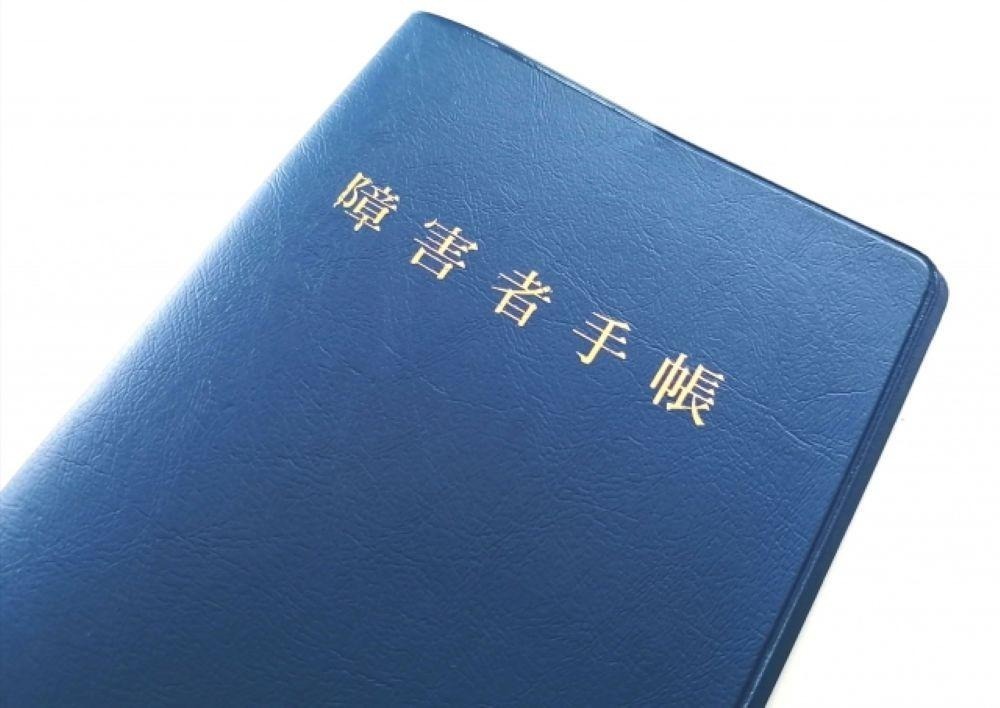
障害者手帳とは、障害のある方が自ら申請して交付を受ける公的な証明書であり、障害の状態や程度を示す役割を持ちます。
障害者手帳を所持することにより、税金の控除や医療費助成、交通機関や公共施設の割引など生活や経済面での支援を受けることが可能です。また、障害者雇用枠での応募や職場での合理的配慮を受けられるなど、就労面でも働きやすい環境づくりに役立ちます。なお、取得するかどうかは本人の意思であり、不要になれば返還も可能です。
障害者手帳は、障害者の社会参加を促進し、自立した生活を支援するための重要な制度です。
障害者手帳は障害ごとに3種類ある

障害者手帳は、障害ごとに以下の3種類があります。
・身体に障害がある方の「身体障害者手帳」
・こころの病を対象とする「精神障害者保健福祉手帳」
・知的障害のある方を対象とした「療育手帳(愛の手帳)」
それぞれについて、詳しく解説します。
1.身体に障害がある方の「身体障害者手帳」
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障害がある方や指定難病を持つ方の自立と社会参加を支援するために交付されます。対象となる主な障害は、以下のとおりです。
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声機能、言語機能、咀嚼機能障害
・肢体不自由
・内臓機能障害
・免疫(ヒト免疫不全)機能障害
障害の種類や重症度に応じて1〜7級に区分されており、7級は2つ以上の障害が重複した場合に認定されることがあります。
2.こころの病を対象とする「精神障害者保健福祉手帳」
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき、精神障害や発達障害が原因で日常生活や社会生活に制約がある方の自立と社会参加を支援するために交付されます。対象となる主な疾患は次のとおりです。
・統合失調症
・気分障害(うつ病・双極性障害など)
・てんかん
・薬物やアルコールによる中毒・依存症
・発達障害(ASD、ADHD、学習障害など)
・高次脳機能障害
・ストレス関連障害
等級は1〜3級があり、症状や生活への影響の程度で判定されます。
3.知的障害のある方を対象とした「療育手帳(愛の手帳)」
療育手帳(愛の手帳)は、知的障害がある方に交付される手帳で、児童相談所や知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方が対象です。名称は地域によって異なり、埼玉県は「みどりの手帳」、青森県や名古屋市では「愛護手帳」とも呼ばれます。
重度のA判定と中軽度のB判定があり、自治体によってはさらに細分化される場合もあります。交付後は原則2年ごとに再判定が行われ、障害の状態に応じて区分が見直される決まりです。
障害者手帳を取得することで得られるメリット

障害者手帳を取得することで、以下のようなメリットが得られます。
・経済的な負担が軽減される
・日常生活を支える支援制度を活用できる
・就労支援が受けられる
それぞれについて、詳しく解説します。
1.経済的な負担が軽減される
障害者手帳を取得すると、税金や医療費など以下のような経済的な負担が軽減される点がメリットです。
| 項目 | 支援内容 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 障害者控除(所得税27万円、住民税26万円) |
| 相続税・贈与税 | 85歳までの年数×10万円控除、3,000万円まで非課税 |
| 医療費 | 医療費の自己負担軽減 |
| 公共料金 | NHK受信料や水道料金の割引・免除 |
| 携帯電話 | 障害者割引プランの適用 |
これらを活用することで、経済面での恩恵が受けられ生活がしやすくなります。
2.日常生活を支える支援制度が活用できる
障害者手帳を持つと、日常生活を支える各種支援制度を活用できます。支援内容は自治体によって異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
| 項目 | 支援内容 |
|---|---|
| 公共交通機関 | 鉄道・バスなどの運賃割引 |
| 公共施設 | 美術館・動物園などの入場料割引 |
| 住宅 | 公営住宅への入居優遇 |
| 教育 | 特別支援教育の受講 |
| 介護サービス | ヘルパー派遣、デイサービスなどの支援 |
これらを組み合わせて利用することで、移動や余暇活動がしやすくなり生活の質が向上します。
3.就労支援が受けられる
障害者手帳を取得することで、就労支援が受けられる点がメリットです。以下のような専門機関が、就職活動や職場定着をサポートしてくれます。
| 支援先 | 支援内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 求人紹介、職業相談 |
| 地域障害者職業センター | 職業リハビリテーション、適性評価 |
| 就業・生活支援センター | 就労と生活支援 |
| 就労移行支援事業所 | 職業訓練、職場体験 |
| 転職エージェント | 求人紹介、定着支援 |
これらを活用することで、職場に適応し、長期的な就労を実現しやすくなります。
障害者手帳を取得して働きたい方の相談を受付中!テレワーク特化型転職エージェント「FLEMEE」はこちら
障害者手帳を取得する際に考えたいデメリット

障害者手帳にはメリットがある一方、以下のようなデメリットも考慮しなければなりません。
・手帳の交付や更新に手間がかかる
・障害者雇用枠での採用が不利に働く場合がある
・障害者と認定されることへの心理的な抵抗感が生じる
それぞれについて、詳しく解説します。
1.手帳の交付や更新に手間がかかる
障害者手帳の交付や更新には手間がかかる点がデメリットです。
申請には医師の診断書が必要となるため、診断書料が発生します。また、申請から交付まで通常1〜3か月かかるため、余裕を持って準備することが重要です。
特に精神障害者保健福祉手帳は有効期限が2年と定められており、更新時には再度診断書の提出が必要になります。窓口への来庁や書類の準備に加え、取得後の定期的な通院や症状管理を手間に感じる方も少なくありません。
2.障害者雇用枠での採用が不利に働く場合がある
障害者雇用枠での採用が不利に働く場合がある点もデメリットです。
障害者雇用枠は、一般雇用に比べて給与水準が低いケースや、企業によっては業務内容や評価制度が別枠になっており、昇進やキャリアアップの機会が限定される場合があります。
一方で、近年はダイバーシティ推進を重視する企業が増え、配慮やサポートが整った職場も少なくありません。障害者雇用枠を選ぶ際は、希望する働き方と合うかを検討することが大切です。
3.障害者と認定されることへの心理的な抵抗感が生じる
障害者手帳を取得する際に、障害者と認定されることへの心理的な抵抗感が生じる点もデメリットの一つです。
障害者手帳を取得する際に、多くの方が「自分が障害者として公的に認定される」ことへの心理的な抵抗を感じてしまいます。しかし、障害者手帳を支援やサービスを受けるための「権利証」と捉えると、前向きに活用しやすくなるでしょう。なお、障害者手帳はあくまで本人の意思で取得するもので、不要であれば返納も可能です。
障害者手帳を取得して働きたい方は

障害者手帳を取得して働きたいと考えている方のなかには、「どこに相談すればいいんだろう?」と悩んでいるケースが少なくありません。理想の職場を見つけたいのであれば、障害者雇用を専門に扱っている転職エージェントの利用がおすすめです。
障害者雇用でのテレワークに特化した人材紹介サービス「FLEMEE」では、障害者手帳を取得した方の就職・転職に関する相談に親身に対応し、希望に合った求人企業を紹介してくれます。
障害者手帳を取得して働きたい方の相談を受付中!テレワーク特化型転職エージェント「FLEMEE」はこちら
まとめ
この記事では、障害者手帳の基礎知識や種類、メリットやデメリットについてお伝えしました。障害者手帳は、障害を持つ方が必要な支援を受けるための公的な証明書であり、取得することで様々なメリットを享受できます。
障害者手帳を取得して働きたい方は、障害者雇用でのテレワークに特化した人材紹介サービス「FLEMEE」がおすすめです。「FLEMEE」は、障害者手帳を取得した方に対して就職・転職を親身にサポートしてくれます。
これらの情報が、障害者手帳を取得して働きたいと希望する方にとって、少しでも悩みごとの解決につながれば幸いです。