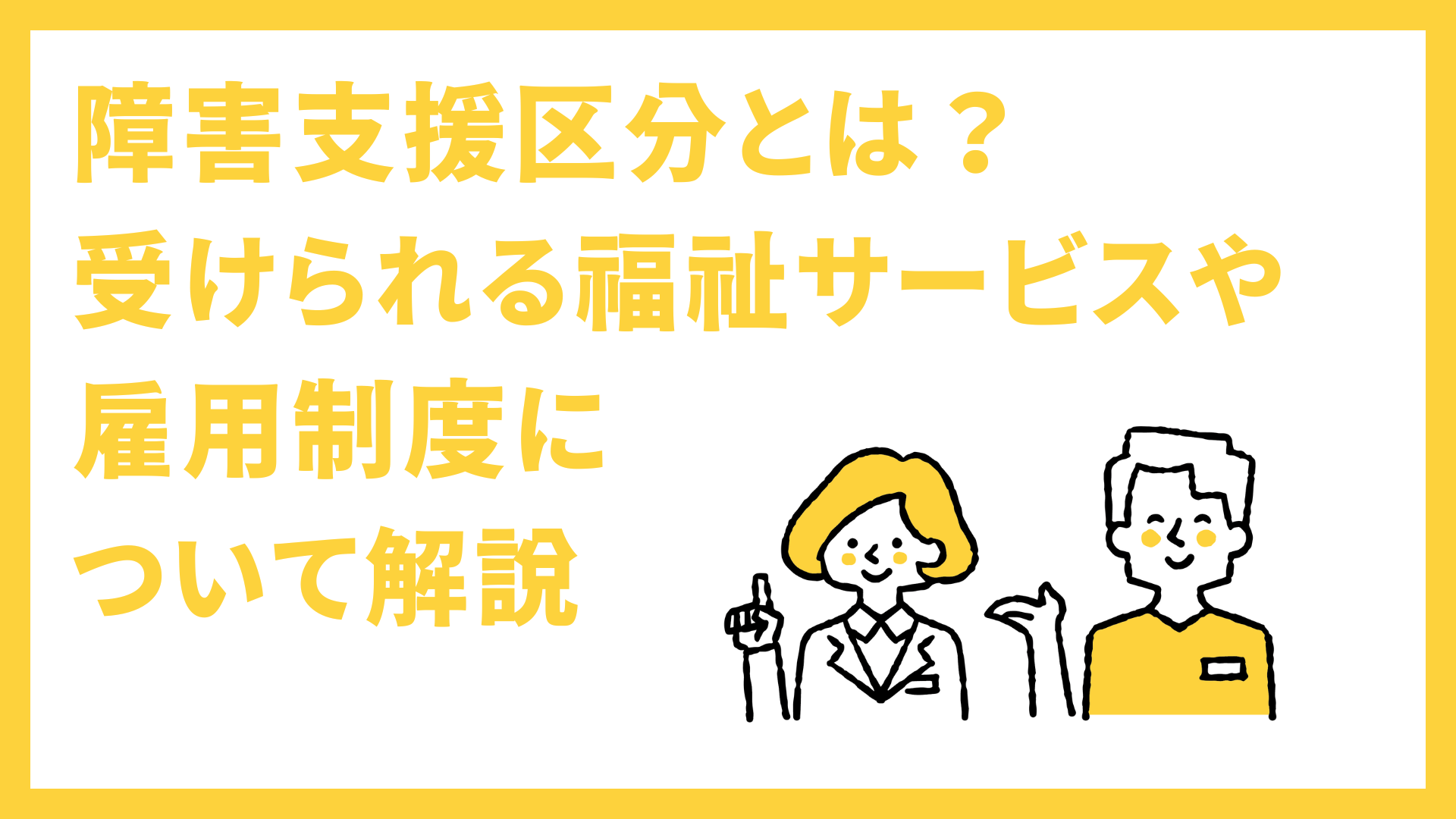障害支援区分とは、障害福祉サービスの利用申請時に、障害の程度や心身の状態に応じて必要な支援を1~6の段階に分けたものです。障害者総合支援法に基づいてさまざまな福祉サービスが提供されています。
この記事では、障害のある方が受けられる福祉サービスや制度について解説しています。障害を抱え、生活や仕事について悩んでいる方の参考になれば幸いです。
障害支援区分とは何か?その目的と重要性

障害支援区分とは、障害福祉サービスの利用申請時に、障害や心身の状態に合わせて必要な支援を総合的に判断し、その程度を1〜6段階の区分に分けたものです。
障害支援区分では、最も支援の度合いが低いのは区分1で、区分6に近づくにつれて支援の程度は高くなります。
また、障害福祉サービスの利用においては、障害支援区分の認定が必要なサービスと障害支援区分がなくても利用できるサービスがあります。
障害者雇用の就職・転職について相談受付中!障害者雇用でテレワークを希望する方におすすめの転職エージェント「FLEMEE」はこちら
障害支援区分の認定調査のプロセス
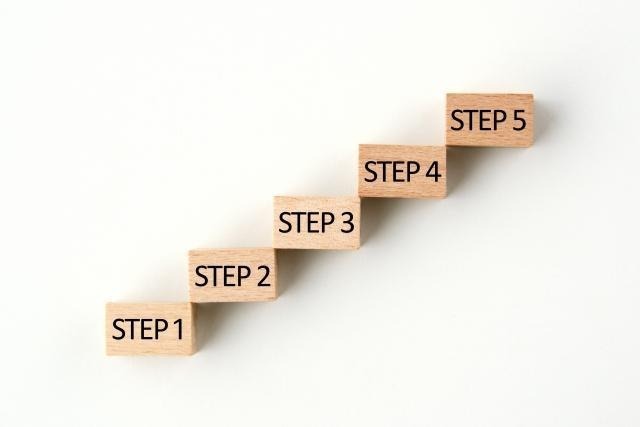
障害支援区分の認定調査は、以下のプロセスで行われます。
1.福祉課などの窓口に申請
2.認定調査員による認定調査
3.一次判定(コンピュータによる)
4.二次判定(市町村審査会)
5.判定
障害支援区分を認定してもらうには、市区町村の福祉担当窓口などに申請が必要です。
認定調査員による認定調査を受けたり、医師の意見書を提出したりします。認定調査結果や医師の意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われます。
その後、市町村審査会による二次判定が行われ区分が決定されるのが一般的な流れです。
認定調査における5分野の評価項目

障害支援区分の認定調査における評価項目は、以下の5つです。
・移動や動作に関連する項目
・身辺自立や日常生活に関連する項目
・意思伝達・コミュニケーションに関連する項目
・行動障害に関連する項目
・特別な医療に関連する項目
それぞれみていきましょう。
第1分野:移動や動作に関連する項目
移動や動作に関連する項目は、以下の12項目です。
・寝返り
・起き上がり
・座位保持
・移乗
・立ち上がり
・両足での立位保持
・片足での立位保持
・歩行
・移動
・衣類の着脱
・褥瘡
・嚥下
褥瘡とは、長期間にわたる寝たきりなどにより、皮膚の血流が悪くなり傷ができる状態です。項目には、褥瘡や嚥下(飲み込み)についても含まれています。
第2分野:身辺自立や日常生活に関連する項目
身辺自立や日常生活に関連する主な調査項目は、以下の16項目です。
・食事の状況
・排せつの状況
・入浴の状況
・掃除や洗濯
・買い物はできるか
・日常の意思決定
・危険の認識
・電話や交通手段の利用
この項目では、食事や入浴、買い物などの日常生活に関連する動作について、どのくらいできるのかを確認します。
第3分野:意思伝達・コミュニケーションに関連する項目
意思伝達、コミュニケーションに関連する項目は、以下の6項目です。
・視力
・聴力
・コミュニケーション
・説明の理解
・読み書き
・感覚過敏・感覚鈍麻
コミュニケーションの項目では、「特定の人ならコミュニケーションがとれる」「会話以外の方法でコミュニケーションがとれる」など項目ごとに定められた基準に沿って、障害の程度を判断します。
第4分野:行動障害に関連する項目
行動障害に関連する項目は36項目で、主な調査項目は以下の通りです。
・昼夜逆転
・こだわり
・暴言・暴行
・多動・行動停止
・集団への不適応
・自傷・他傷行為
・話がまとまらない
この項目では、日常生活での行動上の障害への支援の必要性と頻度を確認します。
第5分野:特別な医療に関連する項目
特別な医療に関連する項目は、以下の12項目です。
・点滴の管理
・中心静脈栄養
・透析
・ストーマの処置
・酸素療法
・レスピレーター
・気管切開の処置
・疼痛の看護
・経管栄養
・モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
・褥瘡の処置
・カテーテル
特別な医療に関する項目では、上記のような医療行為が継続的に行われているか否かを評価します。
障害福祉サービスの根幹「自立支援給付」の概要

自立支援給付は、障害のある方が必要な福祉サービスを利用する際にかかる費用の一部を支給負担する制度です。自立支援給付の種類は、以下の5つが挙げられます。
・介護給付
・訓練等給付
・自立支援医療
・補装具
・相談支援
それぞれ詳しく解説していきます。
介護給付:日常生活上の支援
介護給付は、障害のある方が日常生活を送るうえで必要な介護を受けられるサービスです。介護給付の種類は、以下の通りです。
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・生活介護
介護給付は、障害支援区分により受けられるサービスが異なります。例えば、居宅介護はすべての区分で利用可能ですが、行動援護は「区分3以上」の方が対象です。
訓練等給付:知識・能力向上のための訓練
訓練等給付は、障害のある方が地域で生活するために一定の訓練を受けられるサービスです。訓練等給付の対象となると、以下のようなサービスが受けられます。
・就労移行支援
・就労継続支援
・自立訓練
訓練等給付は、日常生活や仕事に関わる支援を受けたい障害のある方であれば、障害支援区分に関係なく利用できます。
自立支援医療:症状の軽減にかかる医療費の助成
自立支援医療は、心身の障害を軽減させるために必要な医療費を助成する制度です。自立支援医療は、以下の3つがあります。
・精神通院医療
・更生医療
・育成医療
精神通院医療は、精神疾患により継続的な治療が必要な方が対象です。
更生医療の対象は、身体に障害を持つ方で手術や治療により障害の除去や軽減が見込まれる18歳以上の方です。育成医療は、身体に障害を持つ児童(18歳未満)に適用されます。
補装具:身体機能を補完する道具の費用の助成
障害のある方の身体機能を補完する道具を購入・修理する際の費用を助成する制度もあります。身体機能を補完する道具(補装具)として挙げられるのは、車いすや義肢、補聴器などです。
費用の助成を受けることで、購入や修理費の負担を軽減できます。
相談支援:サービス利用の計画・調整をサポート
相談支援は、障害のある方の相談に応じるサービスです。例えば、自立支援給付サービスの利用に関わるケアプランの作成などです。
また、福祉サービスの体験利用や外出への同行など、地域で生活するためのフォローも含まれます。
障害福祉サービス以外の関連支援制度

自立支援給付のような障害福祉サービス以外にも、障害のある方を支える制度として以下2つの制度があります。
・障害者年金
・障害者控除
障害者年金は、病気やけがで障害の状態にあると認められたときに支給される年金です。障害基礎年金と厚生年金があり、加入している年金制度により、もらえる年金が異なります。
障害者控除は、障害のある方やその家族が受けられる所得控除です。障害のある方が受けられる控除には、障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除があります。
障害のある方の仕事を支援する制度

障害のある方の仕事をサポートする制度としては、障害者雇用があります。障害者雇用とは、心身に障害のある方を対象に、一般の採用枠とは別に設けられた雇用形態のことです。
障害者雇用促進法により、企業には障害のある方への差別の禁止や合理的配慮が義務づけられています。一般の求人に比べると数は少ないものの、一般雇用よりも就職しやすく、障害に対する配慮を受けながら働けるメリットがあります。
障害者雇用を希望する方の就職・転職相談受付中!障害者雇用でテレワーク可能な案件も豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
仕事をサポートしてくれる機関

障害のある方の就労を支援してくれる機関は、以下の4つです。
・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・転職エージェント
ハローワークでは、専門の職員が就職の相談に応じてくれます。地域障害者職業センターでは、リワーク支援や職業リハビリテーションを利用可能です。障害者就業・生活支援センターでは、就業面と生活面の一体的なサポートを受けられます。
転職エージェントでは、多くの求人情報から条件に合った求人を紹介してくれます。障害のある方向けの転職エージェントでは、専門のアドバイザーが相談に応じてくれるのが特徴です。
まとめ
障害支援区分とは、障害福祉サービスの必要度合いを心身の状態に応じて総合的に判断し、その程度によって分けるための区分です。
福祉サービスには、自立支援給付のほかにも、障害のある方の生活を支援するために障害者年金や障害者控除といった制度もあります。
また、障害のある方の仕事を支援する制度として障害者雇用があります。障害者雇用で働くと障害への配慮が受けられるため、自分の障害特性に合わせた必要な福祉サービスを受けながら社会的な自立をすることが可能です。
特に、テレワークであれば通勤の必要がなく自宅で自分の体調に合わせて働くことが可能です。テレワーク希望の場合には、テレワーク専門の転職エージェントを利用すると、仕事が見つかりやすいでしょう。
障害者雇用のテレワーク求人を多数扱う転職エージェント「FLEMEE」では、求人紹介に加えのみではなく、障害者雇用の転職活動に必要なノウハウをお伝えするなど手厚いサポートを行っています。
ご紹介した情報が、障害のある方と周囲の方が抱える困りごとの改善につながれば幸いです。