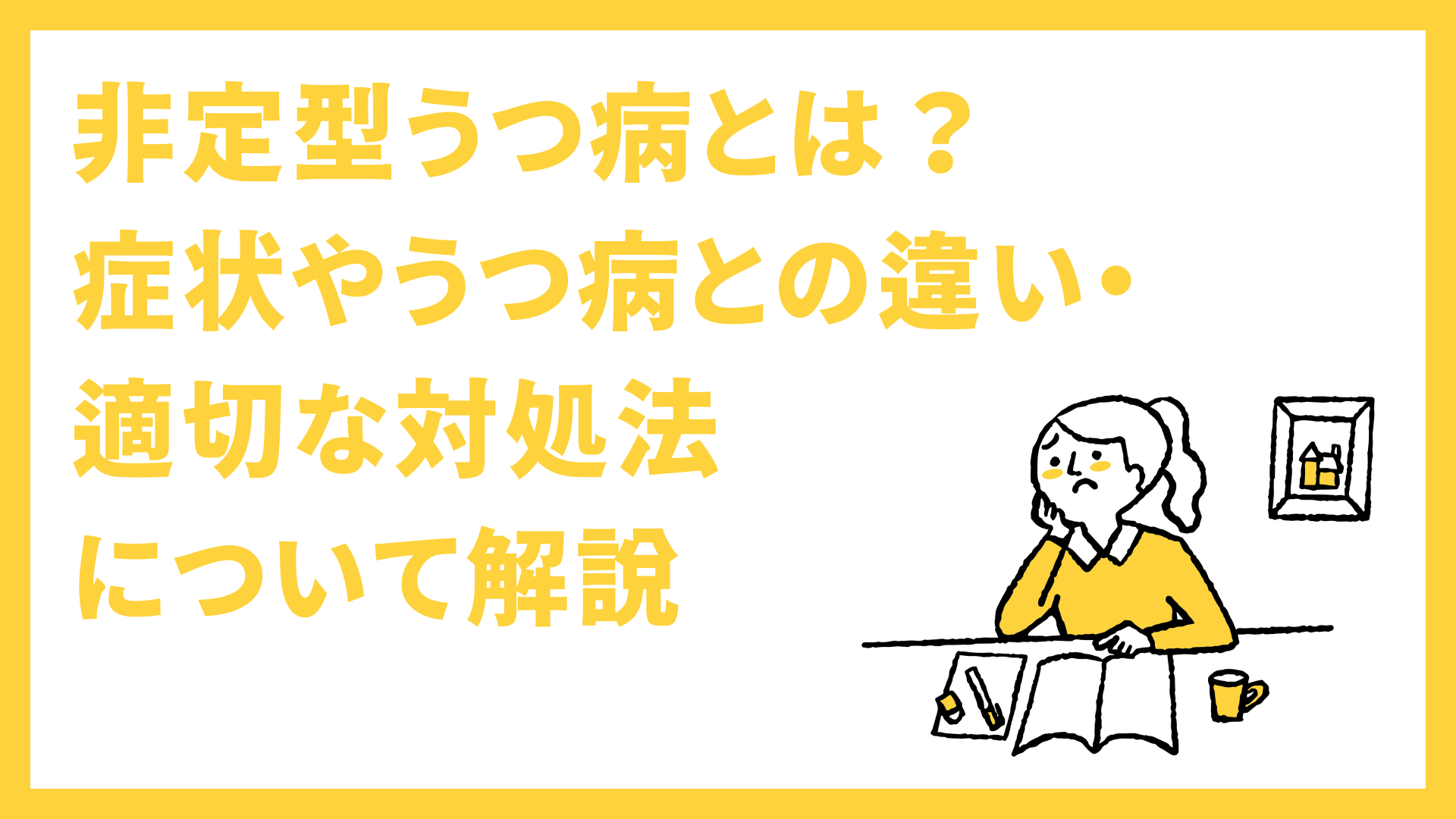非定型うつ病とは、従来のうつ病とはあらわれる症状が違うことにより、単なる甘えや怠けと周囲から思われてしまい、病気と認識されにくいのが現状です。
この記事では、非定型うつ病の特徴やうつ病との違いについて解説しています。非定型うつ病の対処法についても解説していますので、非定型うつ病の症状で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
非定型うつ病の症状を理解している相談員が手厚いサポート!テレワーク求人が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
非定型うつ病の基礎知識

非定型うつ病では、従来のうつ病とは異なる症状があらわれるタイプのうつ病の一種です。
一般的に心の病の診断・治療を行うのは精神科医の役目です。精神科医は診察で専門的な視点から問診や観察を行うことにより、精神疾患の診断の基準である「DSM」または「ICD」に定められている基準を満たすかどうかを考えながら診断を行います。
非定型うつ病はまだ世間一般によく知られていないため、従来のうつ病と異なる症状を目の当たりにした周囲の人々から「単なる甘えではないか」と認識され症状への理解を得にくい一面があるのが特徴です。
しかし、非定型うつ病は、DSM-5-TRでうつ病をあらわす「抑うつ症群」の中に「非定型の特徴を伴う」ものとして記載されているうつ病の一種なのです。
非定型うつ病に見られる特徴的な症状

非定型うつ病によく見られる特徴は、以下の6つです。
1.良い出来事が起こると気分が良くなる
2.他人に拒絶されることへの過敏さがある
3.過食・過眠の症状がある
4.手足が鉛のように重い
5.強い不安を感じる
6.1日の中で体調の変動が激しい
特に1〜4は、DSM-5-TRの診断基準にも記載されている症状です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
気分反応性:良い出来事が起こると気分の改善
従来のうつ病では、良い出来事があっても憂鬱な気分が変わることなく継続します。
しかし、非定型うつ病では、良い出来事が起こったときには落ち込んだ気分が改善して気持ちが晴れやかになります。仕事中は、暗くふさぎこんでいるのに対し、週末は自分の好きなことをして元気に過ごす様子が見受けられるため、それを見た周囲から「ただの甘え」「わがまま」と思われてしまいがちです。
拒絶過敏性:対人関係における過度な不安
非定型うつ病の方は、他人からの拒絶に大きな不安を感じやすいのも特徴です。
例えば、上司にミスを指摘されたときに過剰に落ち込んだり、友人が忙しく会う時間がないときに相手から嫌われたと思い込み過剰に悩んだりすることがあります。
他人からの批判や拒絶を極度に恐れ、相手の言動を悪い方に受け取ったり、人とのコミュニケーションを避けたりします。
食欲・睡眠の症状:過食・過眠
従来のうつ病では、食欲が低下して体重が減ったり、不眠に悩んだりするケースが多いですが、非定型うつ病では食欲が増進し、食べる量が増えるため体重増加が見受けられます。睡眠時間も長くなり、10時間以上睡眠をとっている場合もありますが、よく眠れたという感覚は乏しいのが特徴です。
過食や過眠により、生活リズムが崩れてしまう方も多く見られます。
身体的症状:鉛管様麻痺
鉛のように体が重く感じられるのも非定型うつ病の特徴です。通常の疲労感とは異なり、起き上がったり、座ったりするのも困難な状態に陥ります。
このような重度の疲労感は突然襲ってくるもので自分ではコントロールできません。急に動けなくなる様子を見て周囲から「甘え」「怠けている」と思われてしまいます。
精神的症状:強い不安感
自分の置かれた状況とは関係なく、過去に起きたつらい体験がフラッシュバックし、不安感に襲われるのも非定型うつ病の症状の一つです。
極度の不安感からネガティブな気持ちが強まり、リストカットや薬の過剰摂取など衝動的な行動があらわれる場合もあります。
この病気では、強い不安感による発作的な行動に悩まされるケースが多いのも特徴です。
1日の中で体調の変動が激しい
1日の中で時間帯によって調子が大きく変化することがあり、これを「日内変動」と呼びます。日内変動は従来のうつ病でも見受けられる症状の一つです。
従来のうつ病では、朝が最も不調な場合が多いのに対し、この病気場合は、夕方から夜の時間帯に調子が悪くなるケースが多く見られるのが特徴です。
精神疾患の症状を理解している相談員が手厚いサポート!テレワーク求人が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
非定型うつ病になりやすい方の特徴

男性よりも女性、20代〜30代の比較的若い方に多いのが、非定型うつ病の特徴です。
また、以下の4つが非定型うつ病になりやすい方の特徴です。
・うつ病になったことがある家族がいる
・何らかのトラウマがある
・不安になりやすい
・傷つきやすく周りから良い人だと思われたい
うつ病は、遺伝が関係すると考えられ、家族にうつ病の既往歴があるとうつ病になる可能性が高いです。また、幼少期のトラウマなど深い傷を負った経験がある方もなりやすいと言われています。
性格や気質の面では、不安を感じやすく、他人から良く思われたいと考えるタイプの方はなりやすいと言えるでしょう。
うつ病との違い

非定型うつ病とうつ病の違いとして挙げられるのは、以下の3つです。
・楽しいことには反応する
・過眠や過食が多い
・他人の言動に不安や緊張を感じやすい
従来のうつ病では、何があっても憂鬱や気分の落ち込みが見られますが、非定型うつ病では、良い出来事には反応し、楽しい気分になるのが特徴です。
また、不眠や食欲不振に悩まされる従来のうつ病と比べ、非定型うつ病では過眠や過食により生活のリズムが狂いやすい傾向があります。
従来のうつ病では、自分を責めてしまいがちですが、非定型うつ病は、他人の言動に対して不安を感じやすい方が多いのも特徴です。
非定型うつ病と併存しやすい病気

非定型うつ病と併発しやすいのは、以下のような病気です。
・不安障害
・パニック障害
・双極性障害
・パーソナリティ障害
非定型うつ病は不安を感じやすい気質の方がなりやすいため、不安障害やパニック障害を併せ持つ方が多く見られます。
また、長期間にわたって症状に悩まされると、人間関係のこじれなどからパーソナリティ障害などを引き起こしてしまう場合があります。
回復をサポートする適切な対処法

非定型うつ病の回復をサポートする適切な対処法は、以下の3つです。
・生活習慣を整える
・通院して継続的な治療を受ける
・不規則な勤務形態は避ける
それぞれ解説していきます。
生活習慣を整える
症状の改善には生活習慣を整えることが大切です。しかし、この病気では、長時間睡眠をとっても日中の眠気があったり、食欲が増進して食べ過ぎてしまったりします。そのため、生活リズムを整えるのは難しい一面もあるでしょう。
とはいえ、生活習慣が乱れるとより一層鉛のように体が重くなり、倦怠感を強く感じるなど症状が重くなる傾向にあります。できるだけ生活のリズムを崩さないように過ごしましょう。
通院して継続的な治療を受ける
症状を改善させるには、勝手に断薬したり、通院をやめたりせずに継続的な治療を受けることが大切です。
しかし、非定型うつ病の人は、他人の言動に過敏で不安や緊張を抱えてしまいがちです。上司や同僚の目が気になり「通院で休みたい」と言いにくい場合もあるかもしれません。
病気や通院を続けられるように、職場の上司に相談するとよいでしょう。障害者雇用で就職・転職すると、通院を継続するための配慮が得やすくなります。
不規則な勤務形態は避ける
生活習慣を整えるためにも、夜勤やシフト制などの勤務が不規則な仕事は避けたほうが安心です。特に、非定型うつ病の方は、夕方から夜にかけて不調になる方が多く、生活リズムが崩れると症状が出やすいと言われています。
夜勤やシフト制などの不規則な仕事ではなく、なるべく規則正しい生活ができる仕事を選ぶようにしましょう。
非定型うつ病の方の転職・就職相談受付中!テレワーク求人が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
まとめ
この記事では、非定型うつ病の特徴やうつ病との違いについて解説しました。
非定型うつ病では、強い不安や体が鉛のように重く感じるなどの症状が見られ、良い出来事があると明るい気分になるなどの症状から「単なる甘えと誤解を受けやすい」ことが特徴です。
非定型うつ病もうつ病の一種です。症状が重く、仕事を続けられなくなってしまう場合や、通勤がつらい場合などは障害者雇用での転職・就職を検討するのも一つの方法でしょう。
また、テレワークなら通勤の負担がなく、周囲の反応を気にして調子を崩すことが減る可能性もあります。
障害者雇用のテレワーク求人が豊富な転職エージェント「FLEMEE」では、障害者雇用に詳しいアドバイザーが、転職活動をサポートします。
この記事が非定型うつ病の症状にお悩みの方の助けになれば幸いです。
精神疾患の症状を理解している相談員が手厚いサポート!障害者雇用でのテレワーク求人が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら