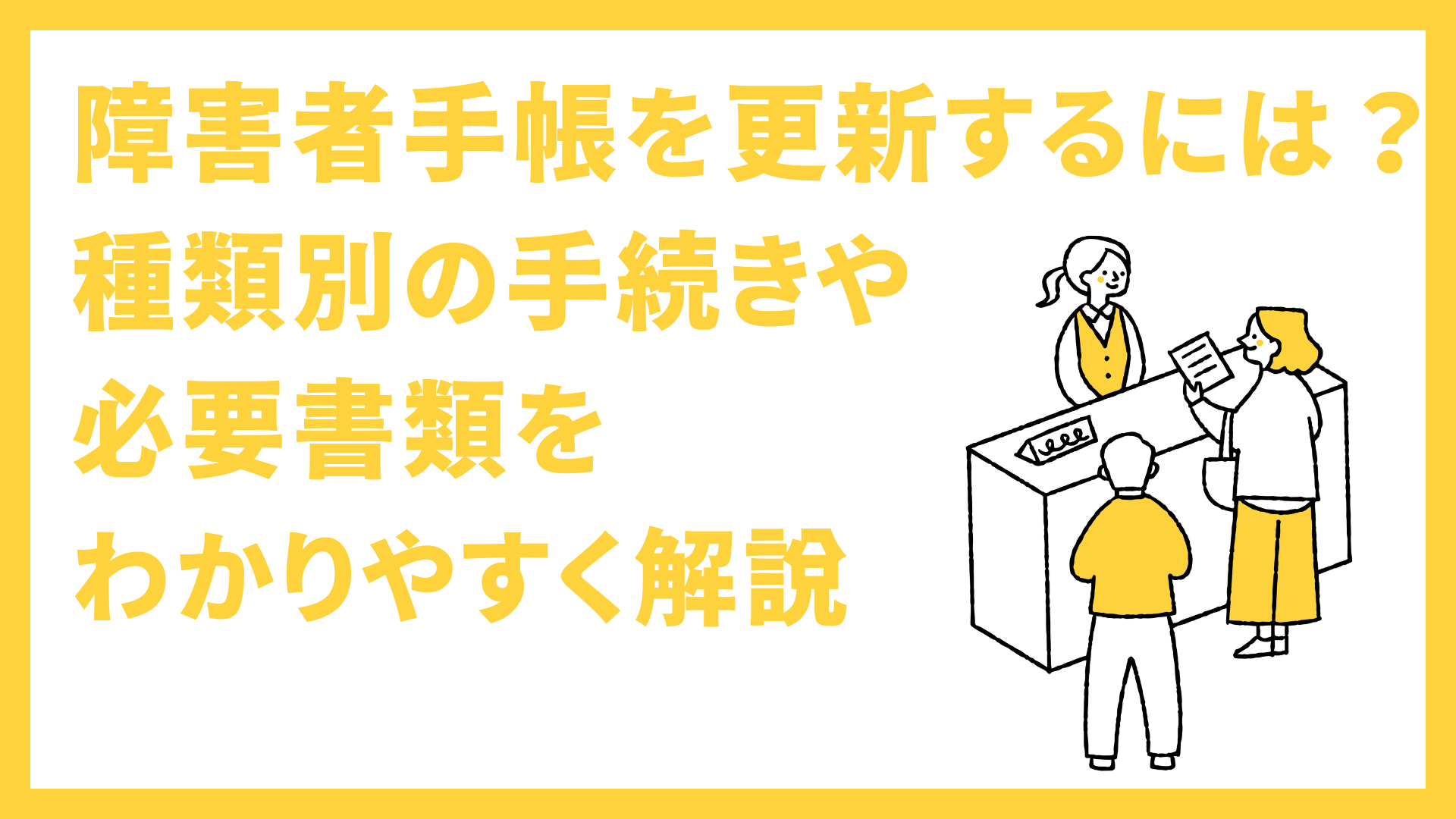障害者手帳の更新時期が近づいてきて、「どんな書類が必要なんだろう?」「手続きは複雑なのかな?」と不安を感じていませんか? 障害者手帳は、必要な支援やサービスを受け続けるための大切な証明書です。
この記事では、障害者手帳の更新を控えている方のために、更新の流れから必要なもの、注意点までをわかりやすく解説します。
更新手続きをしっかり行い、引き続きあなたに合った支援を受けながら、自分らしく働き続けるための第一歩を踏み出しましょう。
身体障害者手帳の更新に関する基礎知識

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき身体に永続的な障害があると認められた方を対象として交付されるもので、障害の程度によって1級(最も重度)から7級(軽度)までの区分があります。
手帳は原則として1級から6級の方に交付されますが、7級の障害が2つ以上重複する場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複する場合も交付対象となります。
障害者雇用の就職・転職について相談できる!身体障害がある方がテレワークできる案件が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
1.原則として有効期限はない
身体障害者手帳には、基本的に有効期限は設けられていません。
ただし、手帳に「再認定年月」の記載がある場合は、その期日までに指定医の診断書を提出し、再認定を受ける必要があります。
再認定の結果によって、等級が変わることがあるため、手帳に記載があるか確認することが重要です。
なお、診断書の発行に時間がかかる可能性があるため、余裕を持って早めに受診しましょう。
2.更新手続きに必要なもの
身体障害者手帳の更新手続きに必要なものは、次の通りです。
・身体障害者手帳再交付申請書
・身体障害者診断書・意見書
・顔写真
・現在お持ちの身体障害者手帳
・本人確認書類
・マイナンバーカード
・印鑑
自治体によって必要な書類や様式が異なる場合があるので、必ず事前に窓口に確認しましょう。
3.更新手続きの流れ
身体障害者手帳を更新する際の流れは、次の通りです。
1.自治体からの通知の確認
2.指定医の受診と診断書・意見書の作成
3.必要書類の準備
4.市区町村の窓口に提出
5.審査・判定
6.新しい手帳の交付
診断書は、身体障害者福祉法第15条で定められた指定医が作成したものに限られており、診断書の発行をしてもらうには指定医の診察を受ける必要があります。
事前に自治体の窓口や病院に指定医の診察を受けられる医療機関について確認しておきましょう。
療育手帳(知的障害者手帳)の更新に関する基礎知識

療育手帳(知的障害者手帳)は、知的障害のある方を対象として交付される手帳です。判定は、主にIQ(知能指数)や日常生活を送るために必要な能力の評価に基づいて行われます。
療育手帳の更新手続きは、基本的に有効期限が定められています。そのため、手帳に記載された有効期限までに更新手続き(再判定)を完了させなければなりません。
1.再判定の期日までに手続きを行う
障害の程度が変わる可能性があると判断された場合は、手帳に再認定年月が記載されます。この期日までに、医師の診断書を提出して再判定を受けなければなりません。
再判定の頻度は、手帳の種類や障害の状況によって異なりますが、成人後、障害の状態が比較的安定していると判断されると、再判定の期間が長くなる傾向にあります。
2.更新手続きに必要なもの
療育手帳(知的障害者手帳)の更新手続きに必要なものは次の通りです。
・療育手帳再判定(または更新)申請書
・現在お持ちの療育手帳
・顔写真
・本人確認書類
・必要に応じて求められる書類(医師の診断書、日常生活状況に関する書類)
・印鑑
必要書類や手続きの詳細は地域によって異なります。そのため、お住まいの自治体に必要書類を確認しましょう。
3.更新手続きの流れ
療育手帳(知的障害者手帳)を更新する際の流れは、次の通りです。
1.自治体からの通知
2.判定機関への予約
3.再判定の実施
4.書類提出
5.新しい手帳の交付
年齢によって判定を受ける窓口が変わります。18歳未満なら児童相談所、18歳以上なら知的障害者更生相談所に予約を入れましょう。
また、手続きに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って早めに手続きを始めることが大切です。
精神障害者保健福祉手帳の更新に関する基礎知識

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき精神疾患により日常生活や社会生活に制約があると認められた方を対象とした手帳です。
交付基準として、精神疾患の初診日から6か月以上が経過している必要があります。
等級は精神疾患の状態と、それによって日常生活や社会生活がどの程度制限されているかに応じて、1級、2級、3級の3段階に区分されます。
障害者雇用の就職・転職について相談できる!精神障害や発達障害の方がテレワークできる案件が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
1.手帳の有効期限は2年
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、原則として2年です。精神疾患の病状は人によって変動する可能性があるため、有効期限が設けられています。
手帳の有効期限がくる前に更新手続きを行い、その時点での障害の状態を確認し、手帳の必要性を客観的に評価することが義務付けられています。
2.更新手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに必要なものは、次の通りです。
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・診断書または精神障害を支給事由とする年金証書等の写し
・顔写真
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
・本人確認書類
・マイナンバー
・印鑑
年金証書で申請する際は、年金の振込通知書や直近の「年金支払額改定通知書」など、年金の受給状況がわかる書類の写しも必要な場合があります。
3.更新手続きの流れ
精神障害者保健福祉手帳を更新する際の流れは、次の通りです。
1.更新通知の確認
2.医師の診断書または年金証書の準備
3.必要書類の準備
4.市区町村の窓口に提出・申請
5.審査・判定
6.新しい手帳の交付
基本的な書類は共通ですが、自治体によって追加の書類が求められる場合があります。そのため、事前に市区町村の窓口に確認しましょう。
障害者手帳更新時の注意点3つ

障害者手帳の更新手続きに不安を感じている方も多いかもしれません。障害者手帳の更新手続きをスムーズに行うには、いくつかポイントがあります。
更新時の注意点を押さえ、適切に手続きを進めましょう。
1.期限の確認と早めの準備
障害者手帳の更新期日を過ぎてしまうと、手帳の効力がなくなり、これまで受けていたサービスや支援が受けられなくなる可能性があります。
どの手帳でも、期日が近づいたらすぐに準備を始めることが重要です。特に、診断書の作成には時間がかかったり、病院の予約が取りにくかったりする場合があるため、早めの行動を心がけましょう。
2.病状の変化を反映する
病状が変わった場合は、障害の等級も変わることがあります。そのため、更新時の診断書には、現在の病状や障害の状態を正確に記載してもらうことが重要です。
専門機関を受診する際は、医師とよく相談し、日常生活で困っていることや、できるようになったことなどを具体的に伝えましょう。
3.相談窓口を活用する
手続きで不明な点や不安がある場合は、一人で悩まずに相談窓口を活用してください。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、かかりつけの医療機関の相談員がサポートしてくれます。申請書類の書き方や今後のサービスについてなどはそれぞれの担当者に気軽に質問するとよいでしょう。
障害者手帳を活かした転職活動の方法

障害者手帳を利用した転職活動では、自分らしく働ける場所を見つけるためのさまざまなサービスがあります。
転職活動に迷ったら、次の相談窓口を活用しましょう。
・ハローワーク:障害者専門の窓口があり、専門の職員が相談に乗ってくれます
・就労移行支援事業所:働き続けるためのスキル習得や職場探し、定着支援までをサポートしてくれます
・転職支援サービス:転職を希望する人と人材を募集している企業の間に入り、転職活動をサポートするサービスです
障害のある方に特化した転職エージェントであれば、障害者雇用に詳しいアドバイザーが相談に乗ってくれるため、安心して転職活動を進められます。
障害者雇用を希望する方の就職・転職相談受付中!障害者雇用でテレワークができる案件が豊富な転職エージェント「FLEMEE」はこちら
まとめ

この記事では、障害者手帳の更新に必要な書類や、更新手続きの流れについてお伝えしました。障害者手帳を更新することで、障害者雇用枠での転職活動を通じ、ご自身に合った職場を見つけられるでしょう。
障害者雇用のテレワーク求人に特化した転職エージェント「FLEMEE」では、障害者雇用に精通したアドバイザーが、転職活動をサポートします。
この記事が、障害をお持ちの方の力になれば幸いです。