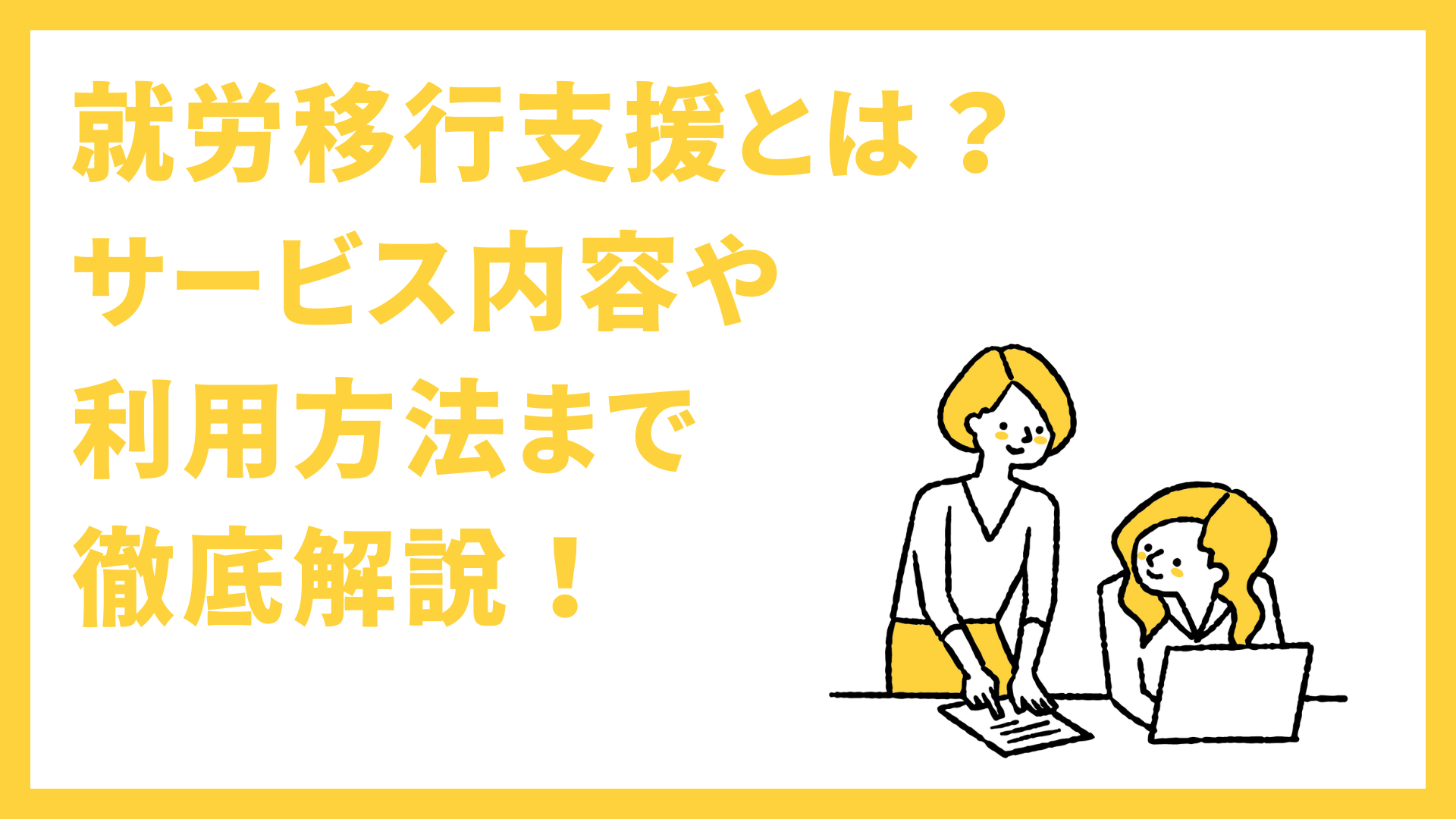FLEMEE 牧野
FLEMEE 牧野こんにちは。FLEMEEの牧野です。
今日は就労移行支援について徹底解説をしていきたいと思います。
就労移行支援とは、障害を持つ方々が一般企業での就労を目指すために提供される支援サービスです。このサービスは、障害を持つ方々が職場で自立して働くためのスキルや知識を習得することを目的としています。就労移行支援事業所に通い、それぞれのプログラムを受講し、一般企業への就職活動や定着支援のサポートを受けることもできます。この記事では、就労移行支援で受けられる主なサービス内容と特徴について詳しく解説していきます。
就労移行支援のサービス内容
まずは、就労移行支援で受けられる主なサービス内容を以下にまとめました。
①職業訓練
就労移行支援では、利用者が希望する職種や能力に応じた職業訓練を受けることができます。
例えば、パソコンの使い方、事務作業、接客業務など、具体的な業務スキルを習得することができます。
②就労準備プログラム
職場の環境や習慣に慣れるための準備プログラムを実施します。例えば、時間管理やコミュニケーションスキル、職場でのマナーなどを学ぶことができます。
③職場実習
実際の職場での実習を通じて、職場環境に慣れる機会があります。このタイミングで、実際の業務は自分の適性やスキルに合っているのかを確認することもできます。
④就職支援
転職活動のサポートを受けることができます。例えば、履歴書の書き方や面接の練習、求人情報の提供など、転職活動に必要なサポートを受けることができます。
⑤定着支援
就職した後も、職場での困りごとに対して対処するための支援を受けることができます。定期的な面談や職場訪問を通じて、安定し長く就労できるようにサポートされます。
就労移行支援を利用するメリット
- 障害特性について自己理解が深まり、職場で理解してもらうためのコミュニケーションスキルが身に付く。
- 転職活動において、履歴書・職務経歴書の作成方法や面接対策などの転職活動のサポートを受けることができる。
- パソコンなどの専門的なスキルを習得できたり、職場で必要なコミュニケーションスキルやビジネスマナーなど基礎的なスキルを習得することもできる。
- 就職した後も、安定就労のためのサポートを受けることができる。



就労移行支援を利用するメリットはさまざまですが、一般企業での就職活動には、自身の障害に対する「自己理解」や「自己対策」をしっかり言葉で伝えることが重要です!
また最近ではIT特化型の就労移行支援やテレワークをするためのスキルを習得できる就労移行支援も増えており、それぞれ利用者のニーズに合わせた機関を選ぶことが重要です。
テレワークに特化した転職先を見つけられる転職サイト「FLEMEE」はこちら↓
就労移行支援を利用できる条件
就労移行支援を利用するためには、以下のような条件があります。
障害者手帳の所持
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
上記のいずれかの障害者手帳を所持していることが条件です。ただし、手帳がなくても医師の診断書だけで利用できる場合もあります。その際は、自治体から就労移行支援の利用に関する認定を受ける必要があります。
18歳以上65歳未満であること
就労移行支援は、一般的に18歳以上65歳未満の方を対象としています。理由としては、就労を目指す年齢層を対象としているためです。
就労意欲があること
就労を目指す意欲があることが必要となります。その就労意欲によって、それぞれ利用者の目標に基づいたサポートが提供されます。
失業中であること
現時点で仕事をしていないことが前提となりますが、休職中や学生などが利用ができる事業所もあります。
就労移行支援を利用する流れ
- 書類の取得:まずは病院へ受診し、医師の「意見書」や「診断書」を取得します。
- 相談窓口に相談:住んでいる地域の自治体の相談窓口に相談します。利用の希望や障害の状況を説明をし、必要な手続きを経て、適切な支援機関を紹介してもらいましょう。
- 支援機関の選定:自治体からの紹介、もしくは体験会などを通じて自分に合った支援機関を選定します。
- 申請と認定:申請する自治体に利用申請を行い、必要な書類を提出します。それをもって自治体が審査を行い、適切であると認定されれば、障害福祉サービス受給者証が発行され許可がおります。
- 個別支援計画の作成:支援機関に相談をしながら、どのように就労移行支援を利用するかという個別支援計画を作成します。その計画書を自治体に提出し、それに基づいて支援が開始されます。
就労移行支援を利用するスケジュールや期間について
就労移行支援を利用する際のスケジュールは、利用者のニーズや支援計画書によって個別に設定されますが、以下には一般的なスケジュール例を記載します。
・支援開始(開始〜3ヶ月):利用者のスキルや適性を見て、最適な支援計画を立てます。コミュニケーションスキルやビジネスマナーなど、基本的な就労スキルを学びます。
・専門訓練(3〜6ヶ月):希望する職種に応じた専門的なプログラムを実施します。(例:パソコンスキル、接客など。)実際の職場での実習を通じて、実務経験を積みます。
・求職活動(6〜12ヶ月):就職サポートとして、履歴書・職務経歴書の作成サポートや面接練習を実施します。支援機関から実際の求人情報の紹介があったり、就職活動を進めます。
・定着支援(12〜24ヶ月):就職が決まった後も、職場への定着支援をサポートします。定期的なフォローアップや職場訪問を通じて、安定した就労を支援します。
一般的にはこのようなスケジュールでプログラムが構成され、就労移行支援の利用期間は原則2年間と定められています。特別な事情がある場合は、自治体の判断により利用期間が延長されることもあります。
就労移行支援を利用する費用について
就労移行支援のサービスを受けるためには、どれくらいの費用が必要か気になる人も多いと思います。実際には、所得に応じた自己負担額が設定されますが、具体的な負担額の具体例は下記に記載します。
| 収入の目安 | 自己負担額 |
| 生活保護受給者・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(概ね年収600万円未満) | 月額上限9,300円 |
| 上記以外(概ね年収600万円以上) | 月額上限37,200円 |
まとめ
この記事では就労移行支援の利用について、サービス内容や利用方法などをまとめました。就労移行支援は、障害を持つ方々が社会に出て自立した生活を送るための重要なステップです。特に転職活動をする上で、自身の障害特性に対する自己理解や対策方法をしっかりと言葉で伝えることができると、企業視点では安定就労を見込める安心材料となります。就労移行支援のサービスを受けることで、自身の可能性を広げ、働く選択肢が増えることを願います。



テレワークに特化した人材紹介サービス「FLEMEE」では求人紹介だけではなく、障害者雇用における転職活動ノウハウもサポート。詳しくはこちら。